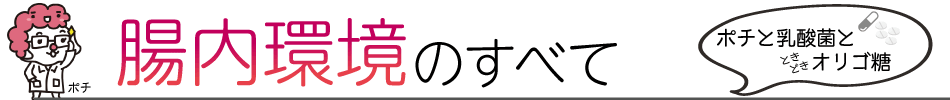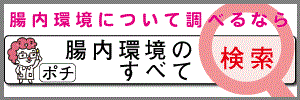腸内細菌の機能、働き
私たちの大腸内で生息する腸内細菌は非常に多岐に渡る働きを担っており、腸内細菌の集まりに過ぎない「腸内フローラ」は、その重要性からもはや1つの臓器として考えられるようになっています。
ここでは腸内細菌、腸内フローラが果たす私たちの身体内での作用、役割について解説します。
腸は第二の脳
口から肛門に至るまでの人間の消化管には、あらゆるところに細菌が宿主である人間と共生しながら生息しており、これらの細菌は私たちの健康的な生活において重要な役割を担っています。
消化管に生息する細菌の数は、口腔部や胃よりも腸、特に大腸に集中していることが分かっています。
特に大腸に生息する細菌を腸内細菌と呼んでおり、約1000種類、数にしてなんと100~1000兆個の腸内細菌が生息していると言われています。
これらの多様な腸内細菌はそれぞれの細菌がその作用を発揮しながら、腸の複雑な機能を支えています。
腸内細菌の構成が変わると腸内細菌によって生成される物質の質や量が変化し、肥満や老化が促進されたり、がんや糖尿病、動脈硬化や高血圧などのさまざまな疾患の要因となり得ることが明らかにされてきています。
また、腸内細菌はさまざまな神経伝達物質の産生・分泌にもかかわっており、脳の働きに作用し、認知症や精神疾患にも関与することが分かっています。
腸は第二の脳と呼ばれるほど、複雑な機能を担い、精神活動にも影響を及ぼす器官で、その機能を支えているのが腸内細菌なのです。
腸内細菌の重要性が、無菌マウスの実験により明らかに
腸内細菌は、空気のあるところを嫌う嫌気性細菌と呼ばれる種類の細菌が多勢を占めており、腸内細菌を使った実験などを行うことが難しく、長く腸内細菌の機能は解明が進まない状態でした。
その後、DNA解析など実験・研究の手法・技術が進歩し、近年になって次々と腸内細菌の働きが明らかにされつつあります。
その中でも、腸内細菌の働き・重要性を確認するための実験として有名なのが、無菌マウスを用いた実験です。
無菌マウスとは、完全に無菌の環境でマウスの赤ちゃんを帝王切開により取り出し、完全に滅菌した水やエサで育成したマウスのことを指し、体内に腸内細菌をはじめ、細菌がほぼ存在したい状態のマウスです。
この無菌マウスと正常なマウスを比較すると、無菌マウスは落ち着きが無い行動を示したり、わずかな物音に対して過剰な反応を見せるなど常に強いストレスを感じているような状態であることが特徴的です。
この無菌マウスに対して腸内細菌叢を移植すると、行動の落ち着きを確認できたことから、腸内細菌が脳の活動にも影響を及ぼすことが実験的に明らかになりました。
また脳との関連以外にも、免疫機能との関連や大腸がんとの関連など、腸内細菌が非常にさまざまな病気や疾患に作用していることが、この無菌マウスを用いた実験により明らかにされてきているのです。
具体的な作用と関連する病気・疾患
腸内細菌はその働きから善玉菌、悪玉菌、日和見菌の3種類に大別されますが、この3種の菌がそれぞれ20%:10%:70%の割合で存在している状態が理想的とされています。
ところがこの割合は食事内容や睡眠の過不足、ストレス、病気への罹患などによって変化してしまうことが分かっています。
腸内細菌の割合が変化し、特に悪玉菌が優勢となると腸内細菌の働きが通常時から変化し、私たちの身体にさまざまな悪影響を及ぼします。
腸内細菌は私たちが生きていくのに必要なエネルギーを産生したり、排便を促すための大腸の蠕動運動や腸での食物の消化・吸収を促進したりするほか、代謝活動の調節、感染から身体を守る免疫機能を活性化したり、悪化すると発癌などの疾患にも関与するなど、さまざまな作用を有することが知られていて、これらが正しく作用しないと私たちの身体は変調をきたすのです。
また、善玉菌、悪玉菌、日和見菌の割合は一定でも、その中で特定の菌種が増殖し、通常時は十分存在するはずの菌種が減少するなど、腸内細菌の構成が変化してしまうような場合にも、腸の作用・働きが変化してしまい私たちの身体にさまざまな異常をもたらす可能性があると考えられています。
腸内細菌の作用
①エネルギー産生や肥満・糖尿病への関与
腸内細菌の中には、食事により摂取した食物繊維を発酵し、酢酸、酪酸プロピオン酸乳酸、コハク酸などの短鎖脂肪酸(Short Chain Fatty Acid:SCFA)を産生する働きを担う細菌があることが知られています。
この短鎖脂肪酸は、肝臓において脂肪を産生するための原料として利用されるなど、私たちが健康な生活を送る上で欠かせないエネルギー源であるほか、さまざまな身体的な機能を担う物質として知られています。
腸内で産生される短鎖脂肪酸は、腸内環境を酸性に保つことで悪玉菌のような有害菌の繁殖を抑制する機能を担っているほか、交感神経を活性化する作用があったり、食欲を抑制するインクレチンと呼ばれるホルモンの分泌を促進したり、細胞内に脂肪物質が蓄積するのを防止する機能を果たしていることが明らかになってきています。
腸内細菌のバランスが乱れるとこれらの機能が正しく働かなくなることにつながり、特にインクレチンの分泌が正しく作用しなくなると、食事をしても満腹感が得られずに過食・肥満に罹りやすくなったり、膵臓におけるインスリン分泌にも影響を及ぼして糖尿病発症の原因となる可能性もあるなど、短鎖脂肪酸の産生の変化がさまざまな身体の変調につながるこのが分かってきています。
また短鎖脂肪酸の産生以外にも、腸内細菌が作用していくつかのビタミンを産生することが分かっています。
ビタミンは基本的に体内で産生することができないため、食事を通して摂取する必要があるのですが、脂肪代謝に関与するビタミンB2や、神経機能に作用するビタミンB6、貧血を改善する働きのあるビタミンB12などのビタミンB群は、腸内細菌の作用によって腸で産生されることが分かっています。
私たちの生命にとって不可欠なビタミンの産生にも腸内細菌は関与しているのです。
②大腸の蠕動運動、消化・吸収の促進
大腸の蠕動運動とは大腸が収縮を繰り返しながら食物の消化・吸収を進めるのとともに、便を肛門側へ押し出すために必要な大腸の作用の1つです。
この蠕動運動も腸内細菌が作用してはじめて、正常に行われるのです。この蠕動運動は自律神経のうち副交感神経により活性化され、交感神経によって抑制されます。
副交感神経は休息時やリラックス時に活発化す自律神経のため、質の高い睡眠を得ることなどが正常に蠕動運動が機能するために必要です。
ところが身体にストレスがかかり交感神経が過剰に活性化され、副交感神経の働きが鈍ると、大腸の蠕動運動が正常に機能しなくなってしまいます。
またこの蠕動運動の機能抑制は、腸内細菌のバランスの乱れによっても生じることが分かっています。例えば悪玉菌が過剰に増殖すると、私たちの身体はこれを排除しようとして蠕動運動を必要以上に活性化してしまいます。
蠕動運動が必要以上に激しくなると、大腸での水分吸収が追いつかずに、水分を大量に含んだ便が排出される下痢の症状を引き起こすことになります。
③免疫システムの維持・活性化
腸は食事をとして摂取した食物など、体外から侵入したさまざまな物質が集まってくる場所です。
このため、必要な栄養分だけを身体内に吸収し、有害な物質を身体内に取り込むことが無いようにするため、免疫機能が非常に発達しているというのも腸の特徴と考えられます。
この腸における免疫機能にも、腸内細菌が作用していると考えられています。
例えば腸内細菌がほぼ存在しない無菌マウスでは、免疫システムを担うIgA抗体と呼ばれるタンパク質や、このIgA抗体の産生を制御する免疫細胞の数が減少していることが分かっています。
つまり腸内細菌が正しく作用することで、免疫細胞が活性化されたり、十分量のIgA抗体が産生されると考えられ、逆に腸内細菌の構成が変化するなどして腸内環境が乱れると免疫システムに悪影響を及ぼす可能性があるのです。具
体的には、免疫反応が弱くなる免疫不全や、逆に免疫応答が過剰になる自己免疫疾患などの病気を引き起こす可能性があると考えられています。
またその一方で、IgA抗体自身が腸内細菌の構成を正しく維持する機能を担っていることも明らかにされてきました。
IgA抗体の量が減少すると、善玉菌が減って悪玉菌が増殖したり、あるいは通常は増殖し無いはずの特定の菌種が増加するなど、腸内細菌の構成が変化することが分かったのです。
腸内細菌と免疫システムは相互に作用しながら、互いが正常に機能するように影響を及ぼし合っているものと考えられ、腸内環境の乱れは免疫システムの乱れを引き起こし、さらなる腸内環境の乱れを招くなど、悪循環につながりかねないと考えられています。
④病原菌から身体を守る感染防御
腸内細菌は免疫システムに作用して私たちの身体を守る機能を果たしているほかにも、また別の方法で外部から侵入する病原性の微生物を撃退する働きを担っています。
病原性の微生物とはさまざまな病気・疾患を引き起こす細菌やウィルスを指しますが、腸内細菌はこれら外来性の病原性微生物に対し、栄養物を自ら摂取して病原性細菌に栄養分が渡らないようにしたり、細菌に対して抵抗性のある抗菌物質を産生するなどして、病原性の細菌やウィルスが腸内に定着・増殖しないように防ぐ働きを担っているのです。
実際、腸内細菌が存在しない無菌マウスではすぐに感染、病気を発症してしまうような病原性細菌を通常のマウスに与えても問題が生じなかったり、あるいは通常のマウスに抗生物質を与えて特定の腸内細菌を死滅させてしまうと、病原性細菌に対する抵抗性が低下することが実験的に証明されています。
このように「腸内細菌vs病原性細菌」の戦いによって、免疫システムを介さずに、感染防御の作用を担うというのが腸内細菌の重要な機能の1つになっています。
⑤自閉症やうつ病などの精神疾患への関与
腸内細菌はいくつかの神経伝達物質の産生にも関与していることが分かっています。腸内で産生された神経伝達物質は血液を介して脳に送られるなどして、私たちの脳の活動や精神状態を変化させます。
このため、腸内細菌の状態によっては産生されるべき神経伝達物質が産生されず、精神状態に変調をきたす可能性があるのです。
帝王切開により出産されたマウスと、通常の出産形式により出産されたマウスでは腸内細菌の構成に違いがあることが分かっていますが、帝王切開により出産されたマウスでは不安行動が多く、うつ病のような症状を示す割合が高いことが知られています。
また腸内ではセロトニンという、私たちが“幸福感”を感じる元となる脳内ホルモン物質が産生されています。
このセロトニンは腸で産生された後、脳で作用し、やる気を引き起こしたり、幸せな気持ちを感じさせたりする機能を担っているのですが、腸内細菌の変化はセロトニンの産生にも影響を及ぼし、幸福感が減少、うつ病のような症状を引き起こす原因になると考えられています。
腸内細菌は神経伝達物質の産生、およびその産生量をコントロールすることなどを通して、私たちの脳にも作用しているのです。
⑥がん発症への関与
腸内細菌の状態により、がんの発症率が大きく変化する場合があることはすでに明らかになっています。
腸内細菌の中には発がんを促進してしまうものもあったり、逆に抑制に関与するものもあります。
例えば、大豆イソフラボンに含まれるアグリコンを過剰に摂取すると、腸内細菌のβ一グルコシダーゼやアゾレダクターゼといった酵素の作用を受けて、発がん物質に変換される場合があることが知られています。
また、衣服やカバンなどの服飾品に含まれるアゾ色素の中には、腸内細菌と作用して毒性の強い発がん性物質に変換されることもあり、この種のアゾ色素を含む染料は「特定芳香族アミンを生成するアゾ染料」として最近になって使用が禁止されました。
一方で、乳酸菌の中には発がんに関連する酵素の作用を低下させたり、発がん物質を分解する作用を担うものもあり、腸内細菌の中にはがん化を抑制する働きがある菌もあるのです。
また、腸内環境が変化し、特定の腸内細菌が増殖することで、その腸内細菌が過剰に作用してしまう場合があります。
この過剰な作用は炎症という形で私たちの身体に影響を及ぼし、炎症性腸疾患、潰瘍性大腸炎といった疾患を引き起こします。
これらの炎症が慢性化することもまた発がんのリスクを高めることが知られており、腸内細菌が慢性的に正常に作用しないことによって生じる消化管の炎症にも注意が必要なのです。
腸内細菌をリセット?便細菌叢移植療法とは
腸内細菌は私たちの身体においてさまざまな機能を担っており、その働きが十分に行われないと、さまざまな疾患を引き起こすことが分かってきています。
これらの疾患の治療するには、腸内細菌が本来の作用を発揮できるよう、腸内環境を正常な状態に戻す必要があるのですが、腸内細菌のバランスは非常に複雑であるがため、その治療は難しいものでした。
しかしながら近年、正常な人の便から腸内細菌を抽出し、それを腸内細菌の機能不全が原因で病気を発症している患者の腸内に移植するという「便細菌叢移植療法」が注目されています。
他人の便を自分の体内に移植すると言うと違和感を感じられるかもしれませんが、動物の世界では他の動物の糞を食べるという行為は一般的で、病原性細菌やウィルスへの抵抗力を高めたり、消化器官の発育促進に効果があることが分かっています。
この考え方を人に適用したのがこの治療法で、健康な人の糞便を生理食塩水でろ過した後、その液体を腸炎患者の腸内に移植したところ、高確率で病気が治癒されたという方向がされています。
一度失ってしまった腸内細菌の作用を元に戻すための治療法として現在も研究が進められている治療方法なのです。
腸内細菌はさまざまな作用、働きを担っており、これらの作用、働きが正しく行われなくなると私たちの身体にさまざまな悪影響を及ぼし、それらが病気という形になって健康な生活の妨げとなってしまいます。
もちろん腸内細菌の作用を元に戻すための治療方法も盛んに研究されていますが、最も大切なのは腸内細菌の機能を低下させないように、良い生活習慣をできるだけ毎日維持することですね。
参考文献
神谷茂:「腸内細菌研究の過去・現在・未来」2016年2月、G.I.Research
実験医学:「明かされる“もう1つの臓器” 腸内細菌叢を制御せよ!」2016年4月、羊土社
内藤裕二:「消化管(おなか)は泣いています-腸内フローラが体を変える、脳を活かす」 2016年1月、ダイヤモンド社
この記事の筆者
腸内細菌博士
1977年生まれ。京都大学・大学院にて分子細胞生物学を専攻。腸による脂質代謝や栄養吸収を細胞レベルで研究、また腸に関連する疾患の予防、治療方法の基礎研究に従事。
ほか、腸の働きと関連性のある自律神経系や免疫システムについては、現在も米国科学雑誌等で最新研究動向をウォッチ中。現在、米国にてMBA留学中。