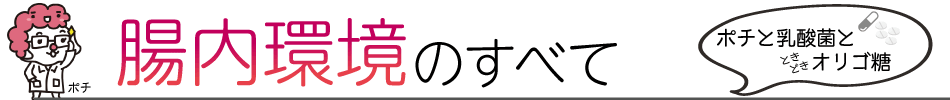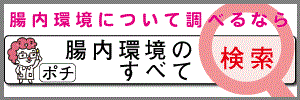腸内細菌と病気の関係性
寒さもようやく峠を越すとやって来るのが、あのユーウツな季節。そう、スギ花粉の飛散です。
皆さんは、スギ花粉症がずっと以前からあったものではないということをご存知ですか? 実はスギ花粉症の歴史は比較的新しく、日本で初めて報告されたのは1963年のことでした。
その後の約50年間、今日に至るまで患者さんの数は右肩上がりで増加し、この時期、オフィスや街中を見渡せばほとんどの方がマスクをしている有様です。
スギ花粉症患者の増加に腸内細菌が関わっている可能性が高い、ということをあなたはご存知でしょうか。
スギ花粉症が増えたわけ
寄生虫研究で名高い東京医科歯科大学名誉教授の藤田紘一郎先生は、「スギ花粉症患者の増加は、現代人の清潔志向に加えて、寄生虫との接触が激減してしまったことと無関係ではない」と指摘しています。
そのご指摘の内容は、「はるか昔から日本人は、回虫などの寄生虫とはある意味で共存していて、体内に寄生虫がいることで、アレルギー疾患で悪さをする抗体をつくらせないようにしていた」というものです。
抗体とは、通常は細菌やウイルスなどの病原体に取りついて、病気を起こさせないようにする、いわば免疫機能の“楯”です。
しかし、スギ花粉症では、スギ花粉を病原体と勘違いしてしまうためにこの抗体がつくられ、その刺激によってあの悩ましい様々な症状がでてしまうのです。
欧米でも同じことが指摘されています。
高脂肪・低繊維の食事、発酵食品摂取の減少、ストレス、運動不足などのほか、生活環境がどんどん改善され清潔になった一方で、それと反比例するようにアレルギー疾患が急増していることが注目され、アレルギー疾患の増加には環境浄化が関係しているのではないかと考えられるようになってきました。
つまり、寄生虫や細菌などとの接触機会が減ってしまったため、体の免疫機能を目いっぱい頑張らせる必要がなくなり、免疫機能がアイドリング状態となってアレルギー疾患に陥りやすくなったのではないかというのです。
事実、多くの患者さんを調べてみると、ある種の腸内細菌が大きく減って腸内細菌の種類が限定され、バランス構成が単純化していることがわかっています。
腸内細菌と病気の関係
腸のなかには約1,000種、100兆個の腸内細菌が存在していると考えられています。これは、ひとを構成する細胞よりもはるかに大きな数字です。
つまり私たちは、自身を構成する細胞の数よりもはるかに多い数の細菌を腸のなかに住まわせているのです。
腸内細菌は、消化されなかった食物のカスを発酵させたり、炭水化物を分解してエネルギーの吸収を助け、かつ病原菌からの防御などの私たちの体にとって極めて重要な役割を担っています。
ですから、この複雑な腸内細菌の集団(腸内細菌叢)をひとつの臓器としてとらえる見方もあります。
そして、より重要なことは、腸内細菌叢がひとの健康上で関係しているのはアレルギー疾患だけに限らないということです。
潰瘍性大腸炎などの消化管疾患、糖尿病、肥満、リウマチ疾患、精神神経疾患、動脈硬化、大腸がんなどについても腸内の環境、つまり腸内にどんな細菌がどれくらいいるのかがひとの健康に大きく関係していることが次第に明らかになってきています。
潰瘍性大腸炎・クローン病
潰瘍性大腸炎やクローン病は炎症性腸疾患と分類される病気で、これまでは主に自身の免疫機能がうまく働かないために起こる病気、「自免疫疾患」と考えられてきました。
しかし、現在有力な説は、ある種の腸内細菌が腸粘膜に棲みついていること、また腸内細菌叢の構成バランスがくずれてしまってことというものです。
肥満
肥満の要因は遺伝と環境の両面から挙げられますが、環境因子として挙げられるのは腸内細菌叢です。
摂取する食物と腸内細菌種との関係が2000年以降、精力的に研究されるようになり、高脂肪・低食物繊維食を摂取する場合の腸内細菌種、低脂肪・高食物繊維食を摂取する場合の腸内細菌種との関係が明らかになり、肥満と腸内細菌叢との関係性が強く示唆されるようになってきました。
高血圧・動脈硬化
高血圧は動脈硬化の果てに起こるものですが、この動脈硬化は血管が体内の様々な分子によって刺激されて起こると考えられるようになってきました。
一方で、腸管からは免疫機能で重要な役割を果たすT細胞や免疫寛容性樹状細胞と呼ばれるものがつくられます。
これらを多くつくりだすように腸内細菌叢を変えることにより、動脈硬化を予防できる可能性があることがわかってきました。
糖尿病
遺伝性の糖尿病(2型糖尿病)患者さんを調べると、腸内細菌叢のバランスがくずれていて、腸内細菌の成分であるリポ多糖体というものが6倍以上も多くなっていることが確認されました。
これによって糖尿病を発症させるインスリンへの反応が鈍くなると考えられています。
これは、逆に考えると、ある種の腸内細菌がつくりだす短鎖脂肪酸がインスリンに対する反応性を改善する可能性を示すもので、糖尿病の治療や予防にもつながるといえます。
がん
腸内細菌との関係では、前立腺がん、乳がん、肝臓がん、大腸がんなどとの関係についての研究が進められています。
特に大腸は腸内細菌の棲みつく場所であることから、以前よりその関係性が指摘されてきました。
大腸がんでは、腸内細菌叢のバランスがくずれたり、優勢となった腸内細菌がつくる物質で大腸の粘膜が刺激されることで粘膜に炎症が起こり、がんの引き金になると考えられています。
関節リウマチ
関節リウマチは「自免疫疾患」のひとつで、自身の免疫機能が悪いほうへ作用してしまうという点でアレルギー疾患と似た側面があります。
その関節リウマチが起きる要因として遺伝と環境があるのですが、一卵性の双子の研究から環境要因が重要であることが確認され、その環境因子として腸内細菌叢の構成の変化が挙げられています。
発達障害
先天的な脳機能の低下によって知的能力に障害がみられたり、コミュニケーションに障害がみられたりしますが、自閉症、多動症などの症状があります。
発達障害のあるこどもでは下痢、便秘、腹痛などの消化器症状を示す場合が多く、その原因として特定の腸内細菌が増えていることが次第に明らかになってきています。
また、マウスによる実験から、腸内細菌がない場合には有害なストレスに過敏に反応することも確認されています。
腸内細菌は健康の“司令塔“
赤ちゃんがお母さんのお腹のなかにいるときには体内に細菌を持っていません。その状態から、赤ちゃんはいわば“バイ菌”だらけの世界にでてくるわけです。
そして、生まれると3~4日程度で腸内に細菌が増殖していることが便から確認されています。こうした腸内細菌の多くは、お母さんから引き継がれていることも遺伝子解析からかわっています。
さらに、ひとりひとりが持っている腸内細菌は生まれて1年以内の生活環境で決定され、それが指紋のように一生変わらないといいます。
つまり、腸内細菌の構成は、生まれた直後に接触したひと(お母さん)から受け継がれ、それがそのひとの一生を通じて通常は変わらないということです。
もし、赤ちゃんにとって腸内細菌が有害であるとすれば、果たして生後3~4日という短期に取り込むでしょうか?
むしろ、赤ちゃんにとって“役に立つ”からこそ、腸内細菌を素早くと取り込こもうとするのではないでしょうか 。赤ちゃんが身の回りのものをなめる行動のわけも、そう考えると納得できます。
腸内細菌の数とバランスが健康の決め手“
腸内細菌の構成を調べてみると、大腸菌やビフィズス菌などの「善玉菌」は、全体の10~20%程度で、「悪玉菌」もほぼ同じくらいで、4分の3は発酵食品に含まれる菌やひとの皮膚などに存在する菌です。
これらは「日和見菌」と呼ばれます。「善玉菌」は食物繊維を栄養源とし、発酵作用を発揮して栄養吸収を助けます。
「悪玉菌」は糖や脂肪を栄養源として有害物質をつくります。「日和見菌」は、ときと場合によって「善玉菌」側についたり、「悪玉菌」側についたり、いわゆる日和見な立場の菌です。
たとえば、腸内細菌のいない無菌マウスに高脂肪・高カロリーの餌を与えても体重は増加しませんが、腸内細菌を棲みつかせると体重は急速に増加していきます。
また、腸内細菌が十分に働いていないと腸は粘膜を正常につくれなくなり、腸粘膜に穴があいてしまいます。
そうなると、栄養素が小さな分子に分解されずに大きな分子のまま体内に侵入してしまい、異物として認識され食物アレルギーを引き起こします。
免疫機能が有効に働き、元気で生きていくためには、腸内細菌の数とバランスが重要で、腸内細菌は、ひとの健康を維持するための“司令塔”のような役割を果たしています。
この記事の筆者
腸内細菌博士
1977年生まれ。京都大学・大学院にて分子細胞生物学を専攻。腸による脂質代謝や栄養吸収を細胞レベルで研究、また腸に関連する疾患の予防、治療方法の基礎研究に従事。
ほか、腸の働きと関連性のある自律神経系や免疫システムについては、現在も米国科学雑誌等で最新研究動向をウォッチ中。現在、米国にてMBA留学中。